
約1300年前から伝わる手間ひまかけて作り上げる贅沢な一品「かつお節」。長い製造工程を経て、カツオのうま味がぎゅっと凝縮され、ほんの少しの量でもその風味を発揮してくれる和食の縁の下の力持ち!食事のベースを掴んでくれるだしとしての利用からさまざまな料理へのちょい足しまで、かつお節の楽しみ方を伝授!今回、かつお節についてヤマキの佐藤さんに詳しくお話を伺った。

佐藤 優さん
ヤマキ株式会社 家庭用事業部
本記事のリリース情報
ウェルビーイングに特化した「Welulu」にて「かつお節」に関するインタビュー記事が公開されました。
約1300年前からある?手間ひまかけて作り上げる贅沢な一品「かつお節」

──かつお節について教えていただきたいのですが、まず原料はどのようなカツオを使用しているのでしょうか?
佐藤さん:かつお節の原料となるカツオは、脂肪分が少ないものが適しています。脂肪分が少ないほうがよい理由は、だしを取る際の濁りや脂が酸化することで変色・風味劣化が早くなってしまうのでそれを避けるためです。
──やはり鮮度のよいカツオを使用することでかつお節の完成度も変わるのでしょうか?
佐藤さん:そうですね、新鮮なカツオを使ったかつお節はうま味が濃く、風味も良いんですよ。例えば、1日に獲れる量だけのカツオを獲る「日帰り漁」というものもあって、カツオを冷凍せずに加工を始めることができます。

──やはり新鮮なものを使うことでかつお節もおいしく仕上がるのですね。
佐藤さん:はい、おいしいかつお節を作るための要素の1つとして鮮度がいいカツオを使うことですが、他にも脂肪分が低いことや解凍方法、燻し方もとても大切です。
かつお節の種類:製造工程編
──では新鮮なカツオを取ったあとのかつお節の製造工程を教えてください。
佐藤さん:かつお節の製造工程はとても手間がかかるもので、まず生のカツオを切って煮ることから始まります。そのあと身から骨を抜き、煙で燻して冷ます工程を6〜15回繰り返したものが「荒節(あらぶし)」となります。燻煙中の煙成分(タール)に覆われることで表面が黒くなり、ゴツゴツしているのが特徴で、培乾香の良い、適度な酸味をもつ味わい深いだしが取れます。
また、カツオのうち、3キロ以上のものは背と腹に分け、節4本分に分けます。これが「本節(ほんぶし)」と呼ばれるものです。小さいカツオは4本に分けず2本に分けるため、その見た目が亀の甲羅に似ていることから「亀節(かめぶし)」と呼ばれます。
──亀節、初めて聞きました!燻す工程があることで、あの印象深い薫香が感じられるのですね。
佐藤さん:はい。その荒節の表面を削ったものが「裸節(はだかぶし)」その後裸節にカビを付けて発育させます。そのカビを「一番カビ」と呼び、さらにかつお節を乾燥させて、再びカビを付けて発育させます。そのカビを「二番カビ」と呼びます。二番カビまで付けて仕上げたかつお節は「枯節(かれぶし)」と呼ばれます。さらにカビつけと乾燥を繰り返したものを「本枯節(ほんかれぶし)」といいます。本枯節の製造には約6ヵ月かかり、うま味が凝縮し酸味が穏やかになって、甘く上品な香りと口当たりがまろやかなだしがとれるんです。
──かつお節といっても、いろいろな種類があるんだ…。カビ菌をつけて乾燥させるのは知りませんでした。
佐藤さん:実はヤマキでは約700種類ものカビ菌を保有しているんです。この中から厳選した優良なカビ菌を使用してかつお節を製造しています。煙で燻すことで水分を飛ばし、細菌の繁殖を抑える効果がありますが、カビの発酵効果でかつお節の水分がさらに抜け、脂肪が分解されてうま味が凝縮されるんです。
──約700種類ものカビ菌の中から選んで使用しているんですね!
かつお節の種類:削り方編
──かつお節の歴史についても教えていただけますか?
佐藤さん:かつお節の歴史は、なんと約1300年前に遡ります。現存する日本最古の歴史書『古事記』に登場している「堅魚(かたうお)」がかつお節のルーツといわれています。また、江戸時代には「勝男武士」とも書かれ、ゲン担ぎの縁起物としても使われていたそうです。
──そういった背景があって、今でも引き出物やお祝い事にかつお節が贈られたりするのですね。
佐藤さん:そうですね。縁起物としてのイメージもあると思いますが、引き出物として送られるようになった背景には、1匹のカツオの半身から、腹肉側の雌節と背肉側の雄節の2種類の節が作られ、雄節と雌節がぴったりとくっつき、夫婦一対を表すためだと言われています。
──一般的に私たちが手軽に使っているかつお節は薄いひらひらのもののイメージが強いのですが、使用用途で削り方を変えているのでしょうか?
佐藤さん:かつお節の削り方には、いくつか種類があり、一般的にスーパーで見かける花かつおやかつおパックなどといった、厚さ0.2ミリ以下のものを「薄削り」と呼びます。薄削りは、冷奴やお好み焼きのトッピング、だしとりなど幅広く使われています。
また、厚さが0.2ミリを超えるものは「厚削り」と呼ばれ、お蕎麦のつゆなどじっくり濃いだしをとる場合に使用されることが多いです。もちろん、厚削りもそのまま食べられます。電子レンジでチンするとパリパリになって、おやつやおつまみにもピッタリな一品が完成します!

──なるほど。よく見かけるのは「薄削り」のものだったのですね。
佐藤さん:薄削りは短時間でさっぱりとしただしがとれるので、お吸い物やおひたしに、厚削りはじっくり煮出して濃いだしがとれるので、そばつゆや煮物に、というように使い分けてみてください。
──それぞれのだしの特性に合わせて上手く使い分けたいですね。

佐藤さん:ほかにも、細長く削った「糸削り(糸がき)」や、さらに細かく砕いた「粉末」などがあります。さらに細かく説明すると切削方法によって「縦削り」と「横削り」があります。
かつお節には繊維があるのですが、その繊維に対して平行に削っているのが「縦削り」で、「花かつお」や薄く削ったかつお節をさらに細かくした「破砕」という種類になります。一方、「横削り」は繊維に対して垂直に削っており、ヤマキでは「マイルド」と呼んでいます。
──繊維に向かってどう削るかで細かく種類が分類されているのですね。ちなみに食感や味わいにはどういった違いがあるのでしょうか?
佐藤さん:荒節・枯節で味わいは変わってきますが、荒節の縦削りは香り・うま味・食感がしっかりしていてソースを使うお好み焼きやたこ焼きにもに負けない存在感があります。一方、枯節の横削りは口どけが良く冷奴やおひたしなど、シンプルな料理によく合うんです。
──かつお節って想像以上に奥が深い!ヤマキさん独自のうま味成分を閉じ込める製法があるとのことですが、どんな製法なのでしょうか?
佐藤さん:カツオの解凍工程を氷温帯(0度以下のカツオが凍る直前の温度帯)でおこなうことで、鮮度の劣化を防ぎ、カツオのうま味成分(イノシン酸)を最大限にキープする製法で「氷温熟成法」という独自の特許製法です。この製造方法で作ったかつお節商品が「氷熟®」といい、弊社商品の中でももっとも多くのうま味成分を含んでいるのが特長です。
──うま味成分がたっぷり詰まったかつお節のおすすめの使い方はありますか?
佐藤さん:私が大好きな「かつマヨトースト」をぜひおすすめしたいです。食パンにマヨネーズと氷熟®のかつお節をかけて焼くだけの簡単なものなのですが、ここにプラスで黒胡椒をかけるとさらにおいしいです。

また、ハンバーグを作る際、パン粉の代わりにかつお節を混ぜたり、から揚げの下味にかつお節を使うのもおすすめです。どちらもかつお節が肉汁を閉じ込めてくれて、ジューシーかつうま味も増して絶品なんですよ。
──ハンバーグに入れるのは意外でした!具材から逃げ出す肉汁は抑えつつも、うま味を与えてくれるなんて。
高たんぱく質食材「かつお節」に含まれるうま味成分

──かつお節のうま味成分についても詳しくお伺いできますか?
佐藤さん:かつお節の代表的なうま味成分は「イノシン酸」です。イノシン酸は、昆布やチーズに含まれる「グルタミン酸」、キノコに含まれる「グアニル酸」と並ぶ三大うま味成分の1つです。
これらの成分を合わせるとうま味の相乗効果でうま味が強くなりさらにおいしさが引き立ちます。
──うま味成分には互いに相乗効果があるのですね。かつお節・だしにはどのような特徴がありますか?
佐藤さん:かつお節やだしは、素材の味を引き立て、味をまとめてくれます。だしを使うと、調味料の使用量を減らしてもおいしい料理が作れるので、減塩料理にも最適です。また、赤ちゃんの味覚形成にも効果的で、かつおだしを使った離乳食は味覚の発達によい影響を与えます。離乳食の初期から使用できるので、時期を見つつ、取り入れていただきたいですね。
──そのほかにどのような栄養素が含まれているのでしょうか?
佐藤さん:たんぱく質も豊富で、かつお節はいわゆる「高たんぱく質食材」なんです。たんぱく質は、私たちの身体のほぼすべての組織を構成し、身体の働きを整えるホルモンにも影響しているので、積極的に取り入れてほしい栄養素です。

──たんぱく質が豊富とのことですが、実際にどのくらいたんぱく質が含まれているのでしょうか?
佐藤さん:削ったかつお節に含まれるたんぱく質の量は、全体の約70%以上にもおよびます。一般的な小袋入りのかつお節パック(2グラム)には、約1.5グラムのたんぱく質が含まれる計算になります。かつお節のたんぱく質には9種類全ての必須アミノ酸も含まれているんですよ。
──ほとんどがたんぱく質!必須アミノ酸にはどのようなはたらきがあるのでしょうか?
佐藤さん:アミノ酸は身体を作るのに必要で、そのうち体内で合成できる「非必須アミノ酸」と、体内で合成できず食事から摂取する必要がある「必須アミノ酸」の2種類があります。
この必須アミノ酸は、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジンの9種類です。これらをバランスよく摂ることができる食材は「良質なたんぱく質を含む食材」とされています。
料理をおいしくヘルシーに!かつお節をもっと楽しむために

──かつお節の研究を始めたきっかけについて教えていただけますか?
佐藤さん:1917年の創業当初から削り節メーカーとして、常に生活者に価値ある商品や情報を提供するために必要なことを探求し続ける姿勢が研究をはじめるきっかけとなっています。
──100年以上の歴史があるなかで、時代の変化に合わせて商品も変化を遂げてきたのでしょうか?
佐藤さん:昔は家庭で削り器を使うのが一般的でしたが、時代が進むにつれて手軽に使える削り商品やめんつゆ・割烹白だしなど、さまざまな形態の商品が登場しました。生活者の生活スタイルやニーズに合わせて商品も変化を遂げています。
──そのほかにも、興味深い研究はなにかされていますか?
佐藤さん:2021年からかつお節の価値・魅力を広める活動「ヤマキかつお節プラス®」を実施しており、産学連携でさまざまな料理とかつお節の相性を研究しています。たとえば、ハンバーグや野菜炒めなどの定番料理から、アイスやみたらし団子などのデザートにまでかつお節をプラスすることで、おいしさや栄養バランスへの影響など新たな価値を発見しています。
──デザートとかつお節の組み合わせは予想外でした!想像がつきません…。

佐藤さん:せっかくならおやつにもかつお節を進出させたいなと思いまして…!かつお節はうま味を足すだけでなく、食感や香りをプラスしてくれます。たとえば、チョコレートアイスや抹茶アイスに細かくしたかつお節をかけると、独特の風味が加わり、意外とおいしいんですよ。
──おいしいのですね、どんな風味がするのかだんだんと気になってきました。
だしの7つのよさ
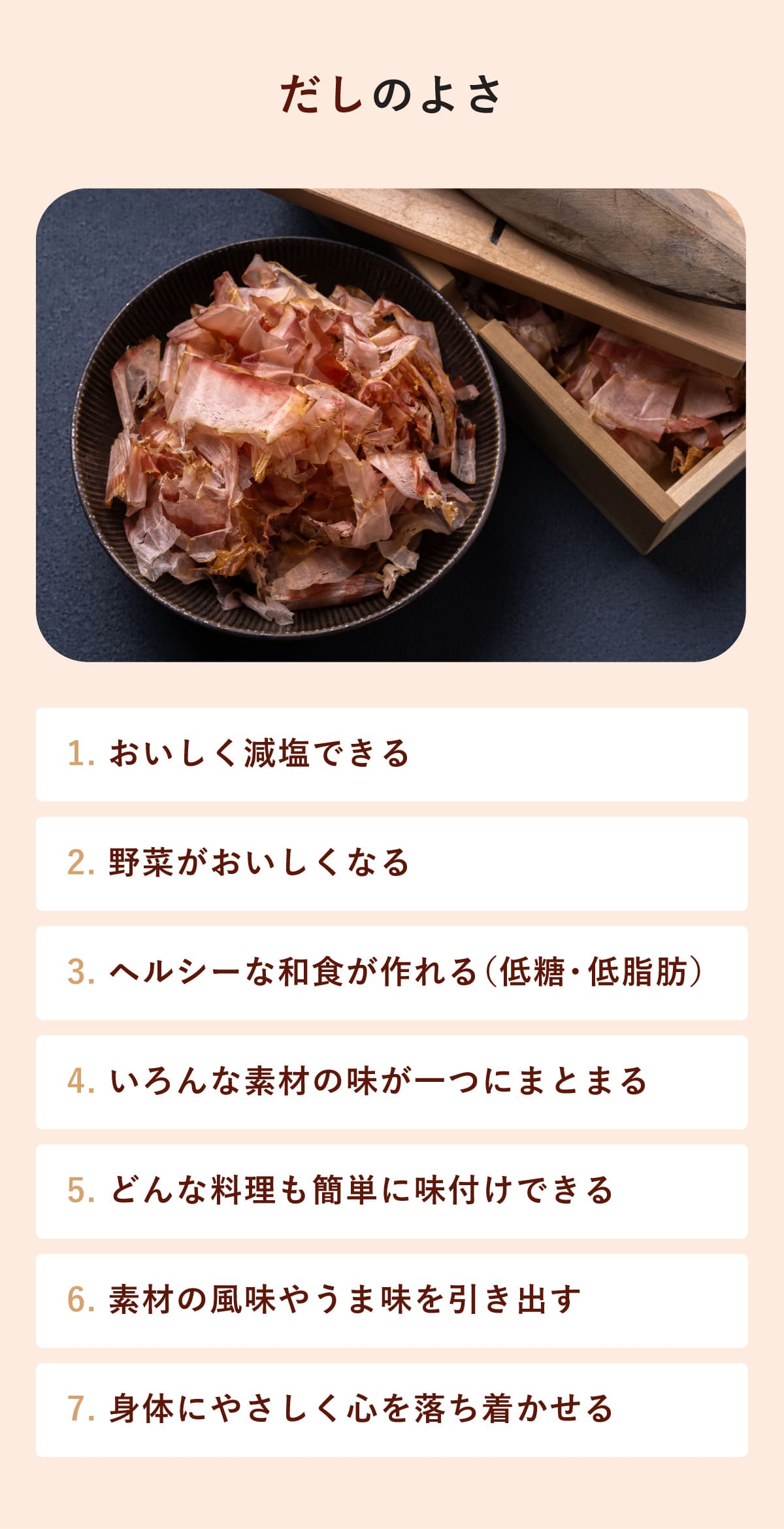
佐藤さん:また、かつお節そのものだけでなく、だしのよいところについても研究をおこないました。
1. おいしく減塩できる、2. 野菜がおいしくなる、3. ヘルシーな和食(低糖・低脂肪)が作れる、4. いろんな素材の味が一つにまとまる、5. どんな料理も簡単に味付けできる、6. 素材の風味やうま味を引き出す、7. 身体にやさしく心を落ち着かせる、これら7つがだしのよさです。
これらのことからも、ぜひ日常の食事にかつお節やだしを取り入れていただきたいと思います。
──確かにお味噌汁を飲むとホッとします。味や栄養価はもちろん、身体だけでなく心にもよい、まさに「ウェルビーイング」な生活にピッタリな食材だと思います。
佐藤さん:そうなんです。今後も生活者の方に必要な情報を提供し、質の高い商品を届けるだけでなく、かつお節の良さをもっと広く知っていただくための情報発信や、普段の料理でより多く使っていただけるような活動も続けていく予定です。
産学連携の研究も継続し、かつお節のおいしさや健康効果を科学的に解析し、そのエビデンスを生活者の方に伝えていきたいです。また、減塩商品の展開や減塩活動にも力を入れていきたいと思っています!
かつお節はだしだけじゃない!かけるだけでうま味・たんぱく質もちょい足し!
──かつお節の1日の摂取目安量を教えていただけますか?
佐藤さん:健康な方であれば摂取目安量はとくに設けていません。かつお節は高たんぱく質で食塩相当量もごくわずかです。極端な食べ方をしなければ、摂りすぎによるデメリットもありません。なので、お好み焼きや冷奴などのイメージが強いかつお節ですが、トーストや納豆、ハンバーグや野菜炒めなど、朝昼晩の食事にかけたり、混ぜたりしてたんぱく質やうま味をちょい足ししてみてください。
離乳食初期の場合は、少量のかつおだしから始めてみてください。通常のかつおだしは、水1リットルに対してかつお節を30グラムの使用をすすめていますが、離乳食で使う際は半量の15グラムでいいです。離乳食中期以降になれば、かつお節そのものも食べられるようになるので、細かくしたものを与えてみてください。
──離乳食の段階に合わせたアドバイスもありがとうございます。

──極端な食べ方をしなければ大丈夫とのことですが、かつお節を摂取するタイミングは朝昼晩いつでもよいのでしょうか?
佐藤さん:はい、いつでも取り入れていただけます。たとえば、朝食にかつマヨトーストとして取り入れたり、夕飯の煮物や炒め物に取り入れるのはどうでしょうか。料理の味が物足りないと感じたときにも、塩や醤油を追加する代わりにかつお節を使うことで、塩分を抑えつつもおいしく仕上げることができます。
──料理中、何か足りないな…と思ったときについ塩や醤油を入れがちですが、まずはかつお節を加えてみるという選択肢があるんですね!そのほかにも、今まで知らなかったようなかつお節の新しい使い方はありますか?
佐藤さん:かつお節は和食だけでなく、洋食や中華料理にも合います。たとえば、麻婆豆腐やチャーハン、餃子にかつお節を加えることで、うま味が増しておいしくなります。餃子の場合、肉汁を吸収してジューシーさを保ちつつ、魚のうま味が加わります。ぜひいろいろな料理にかつお節をプラスして、新たなおいしさを発見してみてください。
──おすすめのかつお節アレンジ料理があれば教えてください。
佐藤さん:おすすめは、野菜炒めです。野菜炒めでありがちなベチャっと感もかつお節を入れることで改善してくれます!また野菜のえぐみや青臭さなどもやわらげてくれるので、野菜嫌いのお子さんのいるご家庭でもぜひ取り入れていただきたいです。沖縄料理のゴーヤチャンプルのトッピングにもかつお節が使われていますが、もしかするとゴーヤの苦味を抑えるためではないかなとも思っています。

また、即席味噌汁を作る際には、お椀にかつお節、味噌、お湯を入れた「かちゅー湯」と呼ばれる沖縄料理もおいしいのでおすすめです。
──「かちゅー湯」気になります!かつお節の正しい保存方法や保管時の注意点についても教えてください。
佐藤さん:かつお節はやはり開けたてがおいしいので、一度で使い切れるのがベストです。袋を開けた瞬間から空気に触れて酸化が始まり、味や風味が落ちてしまいます。そのため、開けたかつお節はなるべく早めに食べ切ることをおすすめします。
それでも使い切れない場合は、チャック付きの商品がおすすめです。中の空気を抜いてしっかり閉じて冷蔵庫で保管してください。もしチャックがない場合は、輪ゴムなどでしっかり留めて保管してください。
──ちなみに、だしをとったあとの「だしがら」は何か活用できたりしますか?もったいないな、と思ってしまって…。
佐藤さん:捨ててしまうのはもったいないですよね!おすすめは、だしがらを細かく切って、めんつゆと絡めて水分がなくなるまで炒めてふりかけにすることです。たんぱく質も余すことなく摂取できます。ぜひ最後の最後までしっかりかつお節をおいしく楽しんでいただけたらと思います!
Wellulu編集後記
原料の鮮度からこだわり、手間ひまかけてできあがるかつお節にもさまざまな種類があり、その風味や食感の違いなど、知らなかったことも多く、驚きました。また、うま味が詰まっているだけではなく、減塩効果といったヘルシーな食べ方にもつながるなど、かつお節の可能性をもっとしっかり活用していきたいなと思いました。まずは普段のお味噌汁から、ひと手間かけておいしいおだしで作ってみたいなと思っています。
