
今回お話を伺ったのは、スポーツ、ビジネスの分野で人材育成のプロフェッショナルとして活躍する中竹竜二さん。早稲田大学ラグビー蹴球部の監督としてチームを連覇に導き、その後は日本代表ヘッドコーチ代行も務めるなど、華々しい成果を残している方だ。
そんな中竹さんは、自律支援型、いわゆるフォロワーシップを大切にする指導方法を牽引してきた人物でもある。「チームで動く」という意味では、関連が深いスポーツとビジネス。チームメンバーがお互いを尊重しながら、チーム全体としてもウェルビーイングな組織になっていくために大切なこととは? Wellulu編集部の堂上研が話を伺った。
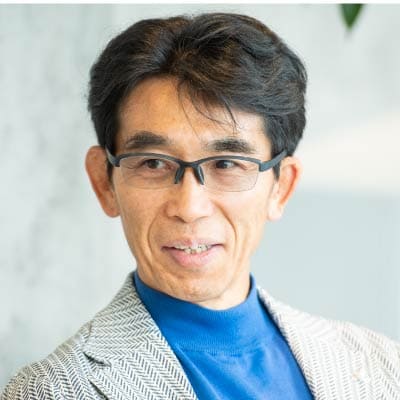
中竹 竜二さん
株式会社チームボックス 代表取締役

堂上 研
Wellulu編集部プロデューサー
1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集部プロデューサーに就任。
「やられキャラ」を武器にコーチのコーチを育てる仕事に

堂上:僕は中竹さんのファンでずっと追いかけていたので、今日こうしてお話しする機会をいただけて嬉しいです。実は、これまで『Wellulu』でお話を伺ってきたなかで「ぜひ中竹さんと対談してほしい!」という声がたくさん挙がっていたんです。本日はどうぞよろしくお願いします!
中竹:光栄です。こちらこそよろしくお願いします。
堂上:まずは中竹さんの経歴とお仕事について伺ってもよろしいですか?
中竹:はい。私はもともとラグビーの選手からスタートして、早稲田大学在学中にはキャプテンを務めていました。社会人になってからは監督として母校に戻り、その後も、U20日本代表や日本代表のヘッドコーチ代行を務めました。
2010年、9年後に日本でラグビーワールドカップが開催されるということで、指導者を育てる「コーチングディレクター」という役割を与えられました。「コーチをコーチする」という仕事ですね。当時、私はラグビーからもう離れようかと思っていたのですが、日本では初めての取り組みだと知って挑戦してみることにしたんです。
堂上:コーチをコーチする……面白いですね。今までなかったのが意外です。なぜ引き受けようと思ったのですか?
中竹:活躍する選手を育てるためには、その選手を育てるコーチを育てることが欠かせません。でも、コーチってほとんどの人が年齢もキャリアも私より上なことが多いんです。私は昔から「やられキャラ」だったので、この役割は私に合っているなと思って引き受けることにしました。
2019年、無事にワールドカップが成功し、その後はラグビーだけでなく、野球、バスケ、バレーなどいろいろな競技のコーチングディレクターを務めることになりました。
堂上:素人の僕からすると、スポーツはそれぞれ全く違うものに見えるのですが、そのスポーツの経験がなくてもコーチングできるものなのでしょうか?
中竹:アスリートのポテンシャルをどう引き上げるかという意味でいうと、コーチやコーチングディレクターという役割はどのスポーツでも共通しています。実はこれって、ビジネスでも同じなんですよね。ひとつの事業を成功させるために、またそこで働く人たちの能力を引き出して成果をあげるために、課長や部長、社長などの役割があるわけです。
堂上:おっしゃるとおりですね。でも、日本のスポーツ界には「コーチのコーチ」という役割はなかったわけですよね。指導の仕方などはどう学んだのでしょうか?
中竹:右も左もわからない状態だったので、まずはイギリスに渡ってコーチングディレクターのライセンスを取得しました。選手をコーチするのと、コーチをコーチするのとでは仕組みが全く違うので目からウロコでしたよ。
ライセンスの取得を通じてコーチング技術を体得して日本に帰ってからは、チームが劇的に変わっていきました。そうするうちに、僕一人では足りないと思うようになり“コーチのコーチのコーチ”のライセンスも取得しました。
堂上:コーチのコーチのコーチ……?
中竹:はい(笑)。私がこれを持っていると、日本でもコーチのコーチのライセンスを発効しながらコーチや選手を育てることができるんです。仲間を増やしたいなと思って頑張っています。
「教える」ではなく「対話」でチームの自主性を育てる

堂上:日本で初の「コーチのコーチ」となった中竹さんですが、今までの価値観がバイアスとなってしまう経験はありませんでしたか? というのも、新規事業を立ち上げているなかで、これまでの常識が壁になってしまうことが多々あるんです。スポーツやビジネスに限らず、同じような場面に直面する方は多いと思うのですが……。
中竹:ありましたよ。ラグビーワールドカップ2019日本大会で活躍する選手を育てるためには、当時(2010年)の高校生を育てるべきだと思っていたので、ターゲットを高校生のラグビー選手に絞ったんです。高校生ラグビーはすでにきちんと仕組み化されていて、選手も指導者も豊富でした。
高校生ラグビーは、全国9ブロックに分かれていてそれぞれ合宿があるのですが、まずはその合宿のやり方を変えることから始めました。練習の一つひとつに対して、練習前のミーティングと練習後の振り返りに、それぞれ2〜3時間ずつかけたんです。毎日夜中の3時くらいまでフラフラになりながら振り返りをした後、朝6時からミーティング……という生活が続いて、コーチ陣から「寝かせろ!」とマジギレされました。コーチ陣にとっては、夜の宴会も楽しみのひとつであり文化でもあったんですよね。
堂上:わかります。でも、そうやってまずは形から変えていったわけですね。
中竹:どうしたら変わるのかなと考えたら、まずはコーチ陣の意識を変えることが大切だと考えました。それに、これは私が監督をしていた時にも思っていたのですが、指導者が学べる場所というのが全然ありませんでした。だからこそ、コーチたちも本当は学びたいはずなんだと信じて続けていたら、2〜3年経った頃にはコーチたちの意識がガラッと変わったんです。
堂上:中竹さんが全国の合宿にわざわざ出向いたり、長い時間一緒に考え続けてきたからこその成果なのでしょうね。
中竹:あとは、私の研修を受けた指導を通して、チームが変わっていったというのも大きいと思います。最初は「なんで後輩のお前に指導されなきゃいけないんだ」という先輩方もたくさんいましたが……。
堂上:ラガーマンなど、いわゆる体育会系は、先輩後輩の縦割りを大切にしている印象があります。
中竹:当時は「すみません、自分でも言いたくないんですけど、そういう役なので……」とやられキャラを全面に押し出していました(笑)。
そして、これまで当たり前だった「指導の方針はトップダウンで落としていく」というやり方をしなかったのも大きかったと思います。幸い私にはフォロワーシップ、いわゆる監督がすべての決定権を持つのではなく、選手が自分で考えて自分で動くことを大切にした指導で早稲田大学を連覇させたという経験があったので、それを今度はコーチの指導に役立てようと、「教える」のではなく「一緒に考える」ことを意識しました。
堂上:良いですね。この「ゆだね」がウェルビーイングにもよく出てきます。任せて自分で考えることで、コーチの自主性を育てたわけですね。
中竹:はい。そうするとチーム自体の結束力もどんどん高まっていき、初めて日本のU19という若手のチームが、ラグビーの本場スコットランドに勝ったんです。それまでは同じ年齢で戦ってくれないほど実力に差がついていました。この勝利を収めたことは、選手にとってもコーチにとっても大きい経験だったと思います。その時の選手たちが、今の日本代表の主力なんですよ。
堂上:めちゃくちゃ良い話……! ラグビーワールドカップ2019日本大会の感動は僕も覚えていますが、そこにはこんな裏話があったんですね。当時、僕は日本で開催されたことを機に、横浜でニュージーランドと南アフリカ戦を観戦して、ラグビーは頭脳戦ということを体感しました。そしてお互いのチームの信頼の先をどうつくるかが大切だと感じました。

堂上:中竹さんは、これまで選手やコーチとのコミュニケーションを大切にしながら日本のラグビー界を引っ張ってこられたわけですが、価値観を押し付けられたり、抵抗されたりした経験はありませんか? 理不尽なことって、世の中たくさんありますよね。 『Wellulu』の読者にも人間関係で悩んでいる方が多く、少しでもヒントになれば嬉しいです。
中竹:大学ではキャプテンを務めたんですが、私はもともと3年生まで一度も試合に出たことがなくて、いきなり4年生でキャプテンになったんです。というのも、これまでは監督や、前の代のキャプテンが次のキャプテンを指名する慣例があったのですが、私の代が初めてそれに逆らって推薦してくれたんです。いわゆるクーデターみたいになって、当時は大問題になりました。
堂上:そんなことがあったんですね……。
中竹:はい。同期の総意だとしても、周りの反応はすごくネガティブでした。先輩から「お前が辞めるって言えばいいんだ」と言われたり、ずっと応援してくれていたファンの方から「早稲田は終わったな」という手紙が届いたり……。
堂上:それは大変な環境ですね。落ち込んだりはしなかったんですか?
中竹:私がキャプテンに立候補したわけではないので、落ち込むことはありませんでしたね。「みんなの力になるから」「みんながいるから」というのが私の原動力でしたし、むしろ使命感がありました。プレーで引っ張れないからと、当時からみんなでとことん話し合うようにしていたんです。
堂上:なるほど。そんな原体験があったからこそ、高校生ラグビーの合宿でも「対話すること」を重視していたんですね。ウェルビーイングと言えば、中竹さんといわれている所以が分かったように思います。
ウサギとカメを戦わせること自体がおかしい?

堂上:ところで、中竹さんは何がきっかけでラグビーを始めたのでしょうか?
中竹:小学校1年生の時に、近所のグラウンドでラグビーチームが結成されたことがきっかけです。最初はサッカーチームの予定だったらしいのですが、教えられる人がいないとのことで急遽ラグビーに変更になったと後から知りました(笑)。
堂上:へぇ! それが中竹さんとラグビーの出会いだったんですね。僕はサッカーをやっていたのですが、僕もたまたま家の近くにサッカーチームがあったことがきっかけでした。当時の練習は、なかなか水を飲ませてもらえない、ミスをしたらグラウンドを10周……なんていう時代でしたが、中竹さんはいかがでしたか?
中竹:同じです。ものすごく厳しかったですね。
堂上:そうですよね。そんな環境でラグビーを習っていたにも関わらず、今は選手やコーチとの対話を大切にしていらっしゃるのがすごいなと思うのですが、意識を変えるきっかけがあったのでしょうか?
中竹:運動能力が低くて、足もすごく遅かったことが関係していると思います。今はサッカーも「オフ・ザ・ボール」といって、ボールを持っていない時間も大切だといわれていますが、昔はもっと運動神経や足の速さが重要視されていました。そんななか、ラグビーは割と早い段階からコミュニケーションなどを含めた複合的な力が必要といわれていて、私にとっては「生き残る術」「ポテンシャル以外で自分が活躍できる場所」だったんです。劣等生のオアシスというか……。
堂上:運動能力以外のところで、チームのために出来ることがたくさんあったわけですね。
中竹:そのとおりです。自分はアスリートには向いていないなと感じつつ、縁の下の力持ちとしてだったら自分でも活躍できると、たまたま出会ったラグビーで感じたんです。
堂上:スポーツをやっている方々にとっては、すごく勇気の出るお話ですね。子どもたちを見ていると、親や指導者の期待を背負わされて自由に楽しめていない子たちが多いような気がします。自分の走りが速くなくても、チームのみんなが走ってくれている間に相手をブロックすることはできますし、それこそがチームスポーツの楽しさでもありますよね。
中竹:それについては『鈍足だったら、速く走るな』(経済界/2011年)という本を出版しています。小学生の時から『ウサギとカメ』の話に違和感を持っていたんです。「調子に乗らないでコツコツ頑張ることが大切」という美談で語られがちだけど、そもそもウサギとカメに「走る」競争をさせること自体が間違っているのでは? と……。
堂上:たしかに、そう言われたらそのとおりですね。小学生の頃にそれに気づいた中竹さんは、やっぱりすごいです。何かきっかけがあったんですか?
中竹:劣等感です。実は私、小学生の頃に自分が読字障害ということに気がついたんです。国語の時間に当てられても教科書が読めなくて、みんなにクスクス笑われたり、先生に「復習してこい」と言われたり。それが悔しくて、徹夜で教科書の内容を暗記してスラスラ読むことに成功したんですが……。
堂上:おお!そこは自分を追い込んだ感じがします。
中竹:「もしかしたら褒めてもらえるかも」と期待していました。でもそんなことは全然なくて、そこで「世の中ってこんなもんなんだ」と思ってしまったんですよね。それからは、褒められたいという欲求は捨てて、人の10倍努力しようと心に決めました。
堂上:素晴らしいですね。僕は『Wellulu』を通じていろいろな方にインタビューさせてもらっていますが、みなさんも中竹さんと同じように「人と比べても仕方がない」ということをしっかり認識されている印象です。周りに「そんなのやっても無意味だよ」「将来のためにはこうすべきだよ」と言われても「鈍感力」で無視して、自分の熱中できるものに集中している。中竹さんにも近いものを感じました。
「本気」かつ「本音」で語ることがウェルビーイングなチームを作る

堂上:中竹さんは5年後や10年後、こうしたいという目標はありますか?
中竹:私は基本的に行き当たりばったりで生きてきて、昔も今も、夢や目標を持ったことがほとんどありません。よく世の中では「夢や目標は持ったほうが良い」といわれていますが、夢を持つかどうかも自由で良いんじゃないかなと思うんですよね。
堂上:わかります。僕も学校で将来の夢を書く課題が出されたら「何になりたいのかなんてわからない」と思っていました。とはいえ、書かないといけないので「社会に役立つ人になる。」とか適当に書いたのを覚えています。特に今の子たちと話していると、小・中学生のうちから夢がある人はほんの一部だと感じます。子どもたちに「夢や目標は持ったほうが良い」と言うのも、大人の価値観の押し付けになってしまっている気がします。
中竹:ドリームハラスメントですね。私みたいに行き当たりばったりの人生もありますから。
堂上:『Wellulu』でお話を伺っている方々は、どちらかというと自分で道を切り拓いてきた方が多いので、中竹さんのお話は新鮮ですごく興味深いです。でも、自ら動かずとも自然と人が集まってくる求心力が中竹さんにはあるように感じるのですが、それはどうしてなのでしょうか?
中竹:簡単です。私に能力がないからですよ。
堂上:みんなに役割を与えて任せている、ということですか?
中竹:それもありますし、もはや助けを求めている感じです。早稲田大学で監督をしていた時も、ある日、選手に「これで勝つっていう方向性を示してください。僕らはどんな辛い練習でも耐えますから」と言われたんです。でも「いやいや、無理だよ」「今までサラリーマンやってた私に、そんな魔法みたいな戦略が出せるわけないじゃん」って。もちろん考えるサポートはしますが、あくまでも選手が主体的に考えられるようにしてきました。
そうこうするうちに、選手のほうが「もうこいつに任せても仕方がない」と思ったのでしょうね。いつしかきちんとフォロワーシップを持って、主体的に行動するようになりました。これまで僕に「ラグビーのこと全然わかってないくせに」なんて言っていた選手たちが、試合の後に胴上げをしてくれたんですよ。
堂上:最高のエピソードですね。中竹さんは本当に素晴らしい指導者なんだと感じます。今でこそ組織の中でも人的資本経営、心理的安全性という言葉がありますが、中竹さんは当時から意識されていたんですね。チームのみんなが言いたいことを自由に言える環境を作ってきた中竹さんは、まさにウェルビーイングという言葉にピッタリな人です。

堂上:とはいえ、チームや組織は意見の食い違いで分断してしまうこともありますよね。たとえば、息子がいたサッカーチームで、「楽しくサッカーをやりたい派」と「強くなって大会でどんどん勝ちたい派」に分かれてしまっていました。それぞれにとってのウェルビーイングを考えると、どちらの主張も間違っていません。こういう時、中竹さんだったらどのようにサポートしますか? やっぱり、とことん対話することが大事なのでしょうか。
中竹:対話させることも大切ですが、誰がファシリテーターとして入るかがかなり重要です。大切なのは「本気」かつ「本音」で語ることができる場を用意することです。
たとえば息子さんのチームの場合、「大会で勝ちたい」と言っている子のなかにはサッカー自体を楽しめていないがゆえにパフォーマンスを落としてしまっている子もいるはずです。一方で「ただ楽しみたい」と言っている子のなかにも、サッカーが上手になることに楽しみを見出す子もいると思います。
「楽しくても勝たなきゃ意味がない」「勝つことばかりに執着したら楽しめない」と意見が対立しているような気がしても、「本気」かつ「本音」で語ってみると、両者が同じことを言っている可能性もあるんです。
堂上:たしかに。そういう意味ではまさに誰がファシリテーションするかが重要ですね。きちんと語り合うことができれば、チーム力、団結力も高まりますもんね。
中竹:はい。ただ、団結力に関してはあまり考えなくても良いと思いますよ。大事なのはまとまることではなくて、「本気」と「本音」があるかどうかです。話し合った結果、さらに分断してしまったら、それはそれで良いと思います。性格上どうしても合わない、生理的に嫌だと感じる人のために大事な時間を使うのは、それこそウェルビーイングではないですよね。
堂上:なるほど。今の話は会社にも通ずる部分がありますよね。「上司や部下と合わない」と言っている人も、「本気」と「本音」で語り合える場があれば、ウェルビーイングに働ける可能性を見つけられるはず。
中竹:おっしゃるとおりです。ただ、みんなが「本気」と「本音」で語れるかと言ったらそうではありません。意識していれば簡単にできるものだと思われがちなんですが、相当な自助努力とメソッドが必要です。だからこそ、自身の会社ではそのファシリテーターの役割を、サービスとして提供しています。
堂上:まさに「外圧」ですね。組織の中だけではできないことを、中竹さんたちのサービスが外圧となってサポートする。これまでチーム内での対話を重要視してきた中竹さんだからこそ実現できる世界なのだろうと思います。ウェルビーイング界隈の方々に中竹さんが推されていた意味がすごくわかりました。中竹さん、どうもありがとうございました!
中竹:こちらこそ、ありがとうございました!

堂上編集後記:
今回、10年前に起業を考えた頃から勝手に憧れていた中竹さんとお会いすることができた。自然体で、笑顔で、自分の弱みも強みもさらけ出せる方だった。だからこそ、たくさんの人たちが、中竹さんがいることに感謝し、自分で行動する人が増えてきたのだろう。
日本のスポーツ文化、会社文化に残っていた先輩や先生は偉いを覆してきた変革者である。そして、どんなときも客観的に、俯瞰で自分を見られている方だと感じた。
会社における組織のウェルビーイングも、いいファシリテーターがいると活気がでる。僕らは、この役割をコミュニティマネージャーと呼んでいたが、その先駆けが中竹さんの挑戦だったことに気がついた。
素敵なご縁をいただいた元同僚に感謝である。中竹さんと一緒に、ウェルビーイング共創社会をつくっていきたい。どうもありがとうございました。
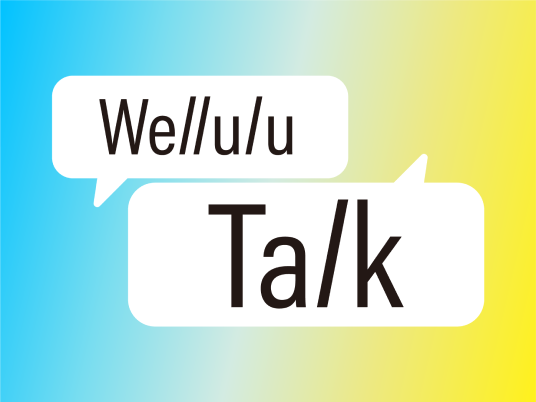
福岡県生まれ。早稲田大学卒業、レスター大学大学院修了。三菱総合研究所を経て、早稲田大学ラグビー蹴球部監督就任。自律支援型の指導法で大学選手権二連覇を果たす。2010年、日本ラグビーフットボール協会 、指導者を指導する立場である初代コーチングディレクターに就任。2012年より3期にわたりU20日本代表ヘッドコーチを経て、2016年には日本代表ヘッドコーチ代行も兼務。2018年、コーチの学びの場を創出し促進するための団体、一般社団法人スポーツコーチングJapanを設立、代表理事を務める。著書に『ウィニングカルチャー 勝ちぐせのある人と組織のつくり方』(ダイヤモンド社/2021年)など多数。